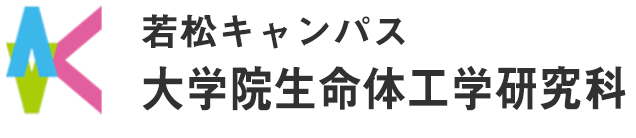生体機能応用工学専攻(博士前期課程2年)
日高 大翔(高嶋研究室)
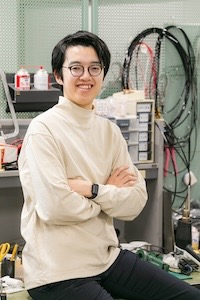
現在、私は生体機能応用工学専攻の高嶋研究室で、カテーテルなどの血管内治療機器に関する研究を行っています。学部時代は戸畑キャンパスで宇宙システム工学を学んでいましたが、在学中に医療機器に興味を持ち、大学院から本研究科に進学し、医工学の研究を行う高嶋研究室に所属しています。
本研究科には、他キャンパスや高専、他大学から進学してきた多様なバックグラウンドを持つ学生が集まり、幅広い分野で研究が進められています。そのため、異なる視点からの意見や知識を共有する機会が多く、専門分野だけでなく他分野の知識も深めることができ、自分自身の成長に大きく繋がっています。
また、本研究科の魅力は幅広い研究だけでなく、海外留学や人材育成プログラムが充実している点にもあります。私自身、昨年の秋に本学の国際交流協定校であるマレーシアプトラ大学でのインターンシップに参加しました。現地の学生とグループワークを行うことで、英会話力や課題解決能力を向上させることができました。
このメッセージを通して、幅広い研究や充実した海外留学プログラムといった生命体工学研究科の魅力が伝われば嬉しいです。皆さんと本研究科でお会いできる日を心より楽しみにしています。
生命体工学専攻(博士後期課程3年)
宍戸 優樺(田向研究室)

現在、私は人間知能システム専攻の田向研究室で脳型AIのアナログ集積回路化について研究しています。他大学の出身ですが、脳型AIとそのハードウェア実装の最前線で活躍されている先生のもとで学びたいという思いから、修士課程から生命体工学研究学科に進学しました。
脳型AIのハードウェア実装には、AIだけでなく脳や電子回路、材料など非常に幅広い知識が必要とされます。その点、生命体工学研究科には多様な分野の研究室が所属しており、研究室間の連携が活発で、学際的な研究を進めやすい環境が整っています。
本研究科では学生へのサポート体制が充実しています。研究指導に熱心な先生が多く、金銭面の支援も豊富なため、安心して研究に集中することができます。さらに、カウンセリング室や学生相談制度によりメンタル面のケアも万全です。留学生も数多く在籍しており、留学支援プログラムも整備されているため、国際的な環境で学び、成長することもできます。
独創的な研究テーマに挑戦したい方はもちろん、高度な専門性を身につけたい、博士号取得を目指している方は、ぜひ一度オープンキャンパスや高専インターンシップに参加することをおすすめします。
この文章があなたの新たな挑戦への第一歩を支えるものになれば幸いです。楽しく過ごす姿を本研究科で見られることを楽しみにしています。
人間知能システム工学専攻(2024年度修了)
鈴木 春名(和田研究室)

現在、私は人間知能システム工学専攻の和田研究室で視覚障害者の単独歩行を支援するシステムの研究を行っています。大学は同学の飯塚キャンパスで情報工学を学び、和田研究室には卒業研究時から所属しています。
私が生命体工学研究科に進学を決めた理由は,様々な背景を持つ人が集まり,協力して研究を行っていることに魅力を感じたからです。例えば、和田研究室では理学療法士や鍼灸師として働いている社会人学生が所属しています。また、大学出身だけでなく、高等専門学校出身の学生や海外の大学を卒業した留学生も所属しています。本研究科は学部がないため、様々な専門知識を持った人が集まり、異なる視点からの意見や知識の共有を行いながら研究を行うことができるため自己成長にもつながります。
また、本研究科は視野を広げることができる点が特徴的です。講義では基礎から学ぶことができ、これまでの知識を活かすだけでなく、新たな学びを得て発展させることができる環境が整っています。さらに、国際マインドなど国外で学び、自分自身へと還元できる機会が多いと感じています。私も研究室内では留学生と触れ合い、文化や言語の違いを肌で感じながら日々勉強をしています。
様々な人と関わり、スキルアップができる生命体工学研究科の魅力が伝われば嬉しいです。このメッセージ読んでくださったあなたと本研究科で会える日を楽しみにしています。
生体機能応用工学専攻(2024年度修了)
百田 風花(就職先:株式会社松風)
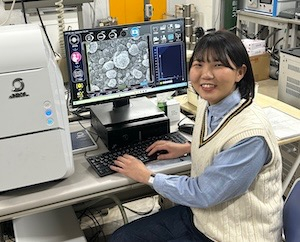
私が本研究科への進学を決めたのは、本学工学部3年次に生命体の教員である宮崎教授の講義で「生体材料」というヒトの体の中で使う材料に出会ったことがきっかけです。材料分野から医療に関われる点に惹かれ、絶対にここで研究したい!と志し、3年後期の早期配属、4年次の卒業研究、そして大学院まで一貫して宮﨑研究室に所属しました。
始めは生体という全く新しい分野に足を踏み入れることに不安がありましたが、工学部出身の学生に向けた生物系の講義や連携研究室の学生との意見交換など、異分野を無理なく学べる環境が整っており、修了時には自身で生物実験を扱えるほどになりました。また、研究室には機械系・情報系出身の学生や留学生も在籍しており、ともに議論を重ねるうちに広い視野で物事を捉える能力を修得できました。
修了後はかねてより希望していた歯科材料メーカーに就職しました。本研究科で身に付けた技術や柔軟な思考力を活用し、材料開発を通して歯科医療の発展に寄与したいと考えています。
生命体工学専攻(2024年度修了)
黒川 侑暉(パンディ研究室)
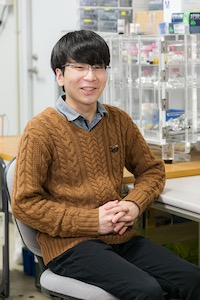
私は、高専で機械工学科に所属し卒業研究のテーマである有機系太陽電池に強く興味を惹かれ、専攻科修了後も研究を続けたいと考えていました。この分野は化学や電気系を専攻する研究室が多く、進学後は研究テーマの変更も視野に入れていましたが、様々なバックグラウンドを持つ学生が所属し、幅広い研究が行われている本学の生命体工学研究科の事を知りました。
幅広い研究だけが魅力ではなく、海外留学や人材育成プログラムも豊富です。私自身、本学の国際交流協定校であるマレーシアプトラ大学とのジョイントワークやインターンシップに参加し、生体機能応用工学専攻だけでなく、持続可能な社会経済を維持し世界をリードする人材の育成を目的としたプログラムであるGlobal Education of Green Energy and Green Environment Courseを修了し、研究以外の活動にも積極的に取り組むことができました。
生命体工学研究科は高専や他大学、他のキャンパスの進学者も多くいます。特に令和6年度の入学者より高専選抜が導入され、専攻科から前期課程への円滑な研究教育の接続が試みられています。自分の進路に迷っている方は、オープンキャンパスや高専インターンシップの参加を強くオススメします。
生体機能応用工学専攻(2023年度修了)
草野 けいと(就職先:Caterpillar Japan LLC)
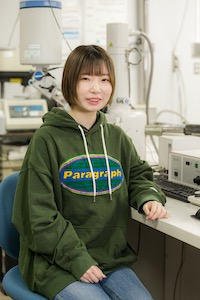
私は生体機能材料研究室(宮崎研究室)にて、化学実験的手法による生体材料の作製と物性評価を行いました。具体的には、がん温熱治療に最適化した強磁性セラミックマイクロカプセルの作製です。私は元々、他大学で機械工学を専攻していましたが、複数の視点で物事を見ることができるジェネラリストのエンジニアを目指し、修士では生命体工学研究科に進学しました。生命体工学研究科の教員と学生の専門分野は、電気、機械、化学、材料、情報、ロボティクス、生物など多岐にわたります。常に異分野交流が行われる機会があり、授業では学部とは異なる様々な知識と技術を学びました。分野を変えての研究は苦労する点も多かったですが、広い視野で工学技術を応用する能力や課題解決力を習得できたと感じます。
私の就職先では、主に油圧ショベルの製造・販売をしています。修士での研究分野と直接的な繋がりは小さいですが、これまでに身に付けた工学技術の応用力と課題解決力で、異分野の課題にも積極的に挑戦していきたいです。
生命体工学専攻(2021年度修了)
岩本 正史(就職先:日東電工株式会社)
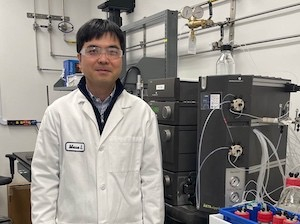
私は、人間知能システム工学専攻、大坪研究室で修士課程を修了し、一般企業に5年ほど勤務した後、仕事をつづけながら博士後期課程に入学しました。会社員として米国で働く中で、博士号取得者への評価の高さや専門性の重要性を痛感しました。大坪教授の指導の下、味蕾細胞の研究で博士号を取得しました。博士課程では、専門知識だけでなく、科学研究における問題解決力、論理的思考、論文の執筆スキルなどを深く学ぶことができました。現在は再び米国で、核酸医薬品製造のトップシェアを持つNitto Denko Aveciaにて、Technology & Innovationグループのリーダーとして、高品質な医薬品を大量製造できる技術の開発に従事しています。研究開発の成果物として、社内外に提出される報告書や特許は非常に重要です。これらの技術文書の作成はもちろん、博士課程で身につけた知識とスキルは、業務において非常に役立っています。迷った際には博士課程での経験が頼りになっています。
生命体工学専攻(2019年度修了)
内田 雅人(就職先:米子工業高等専門学校)
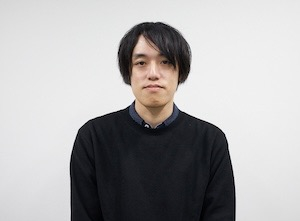
私は人間知能システム専攻の宮本研究室で博士前期課程と博士後期課程を修了しました。また、在学中は産業技術総合研究所と共同で生産設備の異常検知について研究していました。特にAE センサーによるセンシングと信号処理・機械学習による異常検知手法について研究していました。研究を通じて社会実装を常に意識した研究活動ができたことはとても貴重な機会で、人生の財産になったと感じています。また、生命体工学研究科は専門分野が幅広いのが特徴の一つです。学生同士や先生と学生間の交流も盛んで、授業以外でも知見を深める機会が多いと感じました。
研究や日々の生活の中で、自分は人に何かを教えることが好きだと気づき、修了後は母校である米子高専に着任しました。これまで学んだことを意識しつつ、高専らしく身近なものを題材にし、コーヒー生豆の良否判定やロボカップサッカーの戦略 AI を中心に日々学生たちと研究をしています。研究はもちろん、自身が培ってきた技術や知識を次の世代へ繋げていこうと思います。